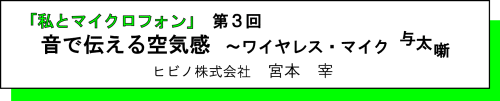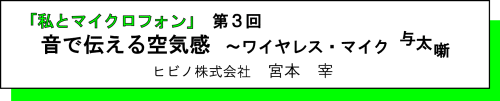|
はじめに
 「私とマイクロフォン」というお題で原稿を、という依頼を申し受けたが、これが特ラ連レポートに載る以上、ワイヤレス・マイクに関して書くべきなんだろう。 「私とマイクロフォン」というお題で原稿を、という依頼を申し受けたが、これが特ラ連レポートに載る以上、ワイヤレス・マイクに関して書くべきなんだろう。
が、しかし、私はワイヤレス・マイクが嫌いだ。特ラ連の理事にあるまじき発言だと言われるだろうが、そう言われても嫌いなものは嫌いなのだから仕方がない。理由は簡単だ。私は音屋だからだ。音屋は普通、安心していい音を出すのが好きだ。もちろん演出に興味が無いわけじゃない。良い演出に裏付けされたパフォーマンスは好きだし、そういうものに関わっていたいとは思う。だから演出からワイヤレス・マイクを要求されたら、できる限り対応していきたいとは思う。でも、緑色のRFメーターがスーッと下がると、心臓の鼓動がドドドッと上がる。スピーカーから「ザッ」とか「バツッ」とかいう音が出ようものなら、首筋から背中に冷や汗が流れ、普段はどんな宗教にも縁が無いのに、その時だけは「神よ!」とか,心の中で叫んでしまう。
この離調・干渉の始末の悪い点は、音屋が入念に準備をしてきて完璧に仕込んでも、隣のホールで無届けのA型ワイヤレス・マイクが使われたり、楽屋裏に突然ENG取材が入ったりすると、すべてが台無しになってしまうことにある。特に野外公演では、それはもう、男の立ちション状態。(あっ、すみません。つ、つまりその、完全に無防備状態だということを言いたくて...)
何が起きても驚いちゃぁいけません。これがリハーサル中に起きてくれればまだいいんだけど、突然本番の最中に起きたりしたらもう完全にお手上げ。
自分達のミスやスキル不足が原因でトラブったら、どんな責めでも受け入れる。でもこれは、いわば不可抗力に近いのに、やっぱり100%音屋の責任になってしまう。こういう時はスペアで切り抜けるんだけれど、ショーの最中にスペアを持ち出すこと自体が、もう大トラブルなわけだから、そのあとはたとえ無事に終わったとしても、ダメ出しのやり玉に挙がる。こういうことを繰り返していたら、誰だって嫌いになってしまうよね。
無線と相対性理論(?)
そもそも、電線で繋がっていないのに信号が伝わること自体がオカシイ! 私の感性は、50年前にテレビ放送が始まった時、みんなで外に出て上を見上げ、空を飛んでくる画を探していた、(とオヤジが言っていた)というレベルにかなり近い。(オヤジの名誉のために言っておくと、オヤジは外には出なかったそうである。ただ、テレビの裏側を何回も覗き込んだらしいが...)
私に言わせれば、携帯電話だって奇跡としか思えない。仕事上、仕方なくその奇跡の産物を使って約4年、最近ようやく慣れてきて、余計なことは考えずに電話ができるようになったのに、先日アメリカはダラスから私の携帯に電話がかかってきて、また悩んでしまった。その時私は、とある都内の会場で仕込みの真っ最中。一方、14時間遅れの地球の裏側の相手は、どっかの飲み屋で“カイバかっ込んで”いるところだった。(テキサス人=カウボーイは、食事をすることをこういう、らしい。)で、話の内容はというと、これがとんでもなく複雑な契約書の話である。こっちはケーブル持ってるし、あっちは“カイバかっ込んで”いる時に話す内容じゃない。こういう重要な交渉事は、上着を着て冷房の効いた明るい部屋で、分厚いファイルとうまいコーヒーを前に置いて、ちゃんと面と向かって話すものだ。でも相手のペースに乗せられて、話はどんどん進んでいく。で、気がついたら、”OK
Richard! Very nice to talk with you. Bye!” なんて満面笑みで、終わっちゃってる。話の結論も、まぁ別に問題ないところに落ち着いている。面と向かって話した時のことを考えると、十数万円の交通費・宿泊費と、ワイシャツのクリーニング代、それより何より数十時間の節約となっている。
こんなことは別に、悩むことでも驚くことでもなんでもないのだろうが、でもちょっと待てよ。よく考えてみると、14時間ビハインドで、1万キロメートル以上も離れた地球の裏側の相手と、リアル・タイムで打ち合わせができた。これは実は、時間と空間と言う、50億年前のビッグバン以来、未来永劫に流れていく、宇宙の深〜い本質に矛盾してるって言えないか?...
携帯電話とアインシュタインの相対性理論を結びつけるのは、ちょっと無理でした。
でも、携帯電話って、ワイヤレス・マイクにとってはちょっと厄介なシロモノだ。使用帯域は800MHz帯が多く、けっこう隣接してるし、出力も、ワイヤレス・マイクはせいぜい0.01ワットなのに対して、敵は0.8ワットと、80倍もある。スタッフ・関係者の皆様、携帯電話をかけるときは、近くにワイヤレス・マイク本体や、アンテナがないことを確認してからかけてください。
無線●−○有線 決まり手=スペック(無線 0勝1敗)
最近のワイヤレス・マイクは、確かに信じられないくらいハイスペックで、しかも高い信頼性を誇っている。でも所詮それは、「昔のものに比べて」というマクラ言葉に続くものだ。有線と無線をスペックや信頼性で比較すること自体、不公平でナンセンスだけれど、面白半分でちょっとやってみると、現在のワイヤレス・システムの伝送系の持つダイナミック・レンジは、コンパンダー方式を使用した場合、だいたい100dB前後だ。対して、シールド線の持つダイナミック・レンジなんて考えたこともないけれど、上のほうは、まぁ恐らく100ボルトくらいは何とか耐えてくれると仮定すると(実験なんかしちゃダメだよ!)、これは42dBuだ。このシールド線を、ワイヤレス・システムが何とか使える見通し距離と同じ、50メートルくらい引き回すと、乱暴に見積もってノイズが-80dBu乗ったとしよう。この時のダイナミック・レンジは約120dBだから、ワイヤレス・システムよりは、まだだいぶ良い。
伝送周波数特性だって、ワイヤレス・システムは40〜15kHzだけど、50メートルのシールド線はDC〜100kHzくらいだろう。
信頼性だって、比べ物にならない...と言いたいとこだけど、へたくそなハンダ付けのおかげで、何回も苦労した過去は否定できません。
とまぁ、ちょっとキベンぽいとこもあったけど、ここでは有線の勝ちだね。
無線○−●有線 決まり手=演出(無線 1勝1敗)
こんなにスペックや信頼性に差があるにも関わらず、ワイヤレス・マイクに軍配が上がるところは、言うまでもなく、その演出的な利便性にある。演出というと少し限定されたニュアンスになるので、言い換えると、ショーやイベント、あるいは演劇を、(はたまた取材も含まれるが)高い品質で成立させるための、中核をなす伝達メディア、とでもしておこうか。で、先にも書いたように、私はワイヤレス・マイクが嫌いなのだが、こうなってしまうとムゲには拒めなくなる。音屋はどういうわけか、『高い品質』とか『高品位』という言葉にとても弱い。音屋の性(さが)みたいなもんだろう。音屋以外の人間から「今日のコンサートの音質は...」とか言われるとムカッとして、ちょっとグレてみたりするが、「もうちょっとコンサートの品質を高めよう。」とか言われると、「ウンウン、じゃあ音屋の立場からは何ができるかな?」なんて、すぐにスナオになってしまう。演出家の皆さん、音屋を説得するには、音屋のそばでそれとなく「これをやってくれれば最高の品質のコンサートになるんだけどなぁ...」とか、「この機材を使ってくれればとても高品位なイベントになるんだけどなぁ...」とかつぶやけば、たいていのことは通りますよ。
ちょっと真面目に...
私が考えるマイクとは、有線であろうと無線であろうと、音場をそのまま切り取ってくるのが、その使命だと思っている。音場と言うと”Off-mic”を想像するけれど、”On-mic”だって近接音場を収音しているのだから、音場を切り取っていることに変わりはない。で、切り取ってきた音場の大きさ・形を整え、(必要なら)調味料を加えて混ぜ合わせ、料理をして、缶詰に入れてラベルを付けて完成させたものがレコード(CD)だ。これが録音屋さんの仕事だ。これの難しい所は、その缶詰を買ってきて食べる人が、どうやって食べるかがわからないところだ。缶詰を開けて、いきなりその缶を手に持って直接割り箸で食べ始める人もいれば、お皿にきれいに盛り付けて、好みの調味料を加えたり、あらためて火を通して食べる人もいるかもしれない。つまり作り手は食べる人の顔が見えないわけだ。
これに対して我々PA屋は、切り取ってきた音場の大きさ・形を整え、(必要なら)調味料を加えて料理をして直ちに目の前のお客さんに出す、いわばレストランの料理人だ。二度とやり直しのきかない、一発の真剣勝負だ。素材の良さを生かせず、味付けや調合に失敗し、まずい料理を出したらたちまちお客のブーイングが来る。でもうまく作れた時、お客と分かち合える感動はまた格別だ。その代わり、同じ物は二度と作れないし、作品として後に残る物は何もない。そんな時、録音屋さんが羨ましく思える。
というわけで、我々PA屋には、切り取ってきた音場を処理した後、最終的に(多くの場合)より広大な空間の中に音場を形作るまでの責任がある。『F.O.H.
Engineerの責任分担はミキシング・コンソールの出力まで。そこからスピーカー・システムのマネージメントまではSystem
Engineerの仕事。』と割り切って仕事をするのは、業務効率とスキルの分配という見地から見ると確かに正しいやり方だとは思うが、だからと言ってF.O.H.
Engineerが音場を全く意識しないでミキシング作業をするのは明らかに間違っている。最終的に形成する音場を意識することなしに、元の音場を切り取ることなど到底できないと思うからである。
音場という言葉を使ったとき、しばしば「定位」と混同されるけれど、「定位」は音場の一部ではあるけれどすべてではない。音場の一番重要な要素は、「空気感」とでも呼ぶべきものだろう。この「空気感」というものはかなりビミョーな代物で、たとえば完璧に定位が制御できていたとしても、音の大きさが不適切だったりすると、たちまち消えてなくなってしまう。また、マイク間のカブリも影響するし、音源同士やスピーカーとの相対距離がかなり強く関わってくる。最近のデジタル・ミキサーでこの相対距離を制御することができるようになったことは、とても大きな利点だと思う。実際、デジタル・コンソールの各入力に備わっているディレイ機能を駆使することで、シンフォニー・オーケストラの「空気感」が、従来よりもだいぶ改善できたことがあった。
ところで、最近のコンサートの中に、「空気感」が感じられないものが増えてきたように感じるのは、私だけだろうか。コンサート会場で、巨大な“ヘッドホン・ステレオ”を聴いているような錯覚に陥ることが時々ある。「ロックに空気感なんてないし、そんなものいらない。」という人もいる。それはある意味、正しい。コンサートが、CDの音を大音量で忠実に再生しようとするならば、である。でも、演奏中にステージで聞いてみると、そこには紛れもなく「空気感」が存在する。そこでは、生身の人間達が汗を飛び散らせて演奏しているわけで、シークエンサーがサンプラーを叩いているわけでもなければ、CDが回っているわけでもない。
話はどんどん横道にそれていくが、「空気感」の最高峰はやはりシンフォニー・オーケストラだろう。私の世代の音楽の授業というと、音楽室の教壇の上に電蓄がドンと置いてあって、時々、ベートーベンの「運命」や、ヨハン・シュトラウスの「ラデツキー行進曲」の“鑑賞会”があった。(この鑑賞会の日は、ピアノ伴奏で退屈な唱歌を歌わなくてもよく、レコードを聴いているフリをして安眠できたので、結構人気があった。話は飛ぶけれど、「小澤征爾&ウィーン・フィル・ニューイヤー・コンサート2002」の中に収録されている「ラデツキー行進曲」は、オリジナルは
=120くらいなのに、 =100くらいで演奏していて、これがまた妙に気持ちが良くて、体内リズムを刺激したなぁ。)以来、私にとってのクラシック音楽は、音楽室の電蓄の中にあったのだが、10年程前、二人の娘が小学校の管弦楽部に入って、体育館での練習を手伝いに行った時に経験した音場は、大きなカルチャー・ショックだった。演奏自体は所詮小学生だからたいした事はないんだが、(といっても、この部はその年の秋に、なんと全国1位になってしまうのだけれど)彼女らが奏でるリムスキー・コルサコフの「交響組曲シェヘラザード」は、どんな名演奏のレコードよりも、(自分の娘達が演奏しているという思い入れを差し引いても)感動的だった。100近い音源が空間で綾なす音場に比べて、どんなにパワフルであっても、たった二箇所のPAスピーカーの生み出す音場の、何と味気ないことか。(こういう比較がオカシイと言えば、確かにその通りだけど)それ以来、生のシンフォニー・オーケストラの音場がずっと気になっていた。1999年末、ディズニー映画の「FANTASIA
2000」のワールド・プレミア・ツアーが、120人編成のロンドン・フィルハーモニー・オーケストラによって演奏されたのだけれど、そのリハーサルの最中に舞台上で楽器の間を歩き回った時に浴びた音のシャワーは、それはもう言葉にならない、全身トリ肌の世界だった。そして、この音場のトリコになって以降、何回かシンフォニー・オーケストラと一緒に仕事をする機会に恵まれたが、やはり生の「空気感」を知ってしまった身にとっては、いろいろなPAシステムへのアプローチは試みたものの、どれも満足からは程遠いものだった。今、生のシンフォニー・オーケストラの音場を、そのまま大空間の中に散りばめることができたら、どんなに素晴らしいだろうかと思わずにいられない。各音源の倍音構成、指向性、奥行き感などが複雑に絡み合った音場を、そっくり漏らさず切り取ることのできるマイキングの手法があるんだろうか。そしてそれらを忠実に空間に散りばめるためには、どんな音響システムが必要になるのだろうか。IMAXという映画のフォーマットがある。ここで感じられる「空気感」は、普通の映画のそれとはだいぶ違う気がする。映画のことは素人だが、空間を取り込むツール(つまりレンズだね)が違うんだろうか。それと再生する空間も、普通の映画館とは違うようだ。音の世界でも、こんなダイナミックな音空間が出せたらいいね。
私に残された時間もだいぶ少なくなってきたようだし、残りの時間を、この「空気感」を求めてちょっと頑張ってみようかな。
ワイヤレス・マイクの話が、とんでもない方向に行ってしまいましたが、「空気感」というものを考えると、マイクのセッティングの自由度という要素は、より重要になっていくと思われます。マイクの仕込みがマイク・ケーブルの束縛から解放されたとき、音場を望むがままに、自由に切り取ることのできる可能性は、より大きくなります。そうなると今度は、使用電波のチャンネル数も現在とは比較にならないほどの数が必要となるだろうし、スペックも有線と同等以上が要求されます。つまりそれは必然的に、デジタル・ワイヤレス・システムに辿り着きます。技術的にはもうほとんど手の届くところまで来ているようですが、問題は方法論、つまり電波の割り当てです。放送も通信もますます多様化してきている現在、ワイヤレス・マイクを巡る環境は決して楽観視できる状態ではないと思われます。こんな中で、多チャンネル・高品質を求める時、どこかで妥協が必要となるかもしれません。それはたとえば、出力を弱くして、その代わりに複数のペア・アンテナの位置を、きっちりとゾーニングで導き出し、緻密に網羅するのか、赤外線のような電波法の及ばない領域を併用するのか、みんなで知恵を絞っていく必要があります。
数日前、不思議な夢を見ました。そこでは有線マイクというものが完全に姿を消し、マイクと言えばワイヤレス・マイクのことを指しているのです。どこの音響機器メーカーも必死になってワイヤレス・マイクを生産しており、それでも需要に追いつかない。昔、ケーブル・メーカーだった企業は、乾電池をフル生産しています。その時、「特ラ連」は、早稲田から霞ヶ関に移転しており、名称も「マイクロフォン運用調整省」になっていました...とさ。
|
|
|
宮本 宰(miyamoto@hibino.co.jp) |
|
|
Hibino Sound/GM |
|
|